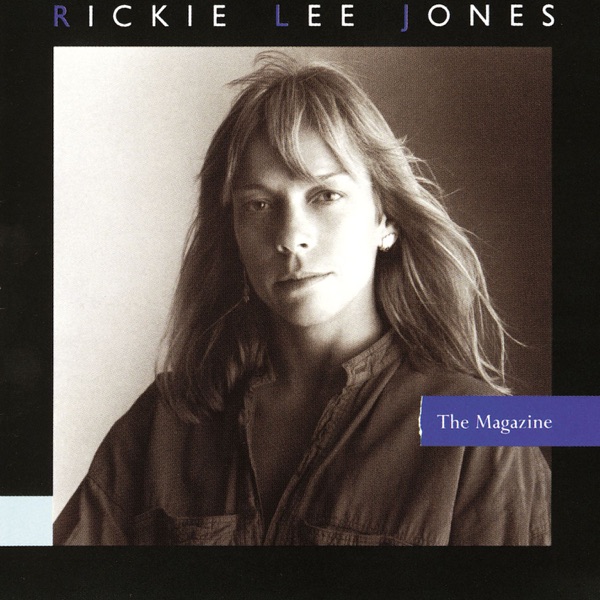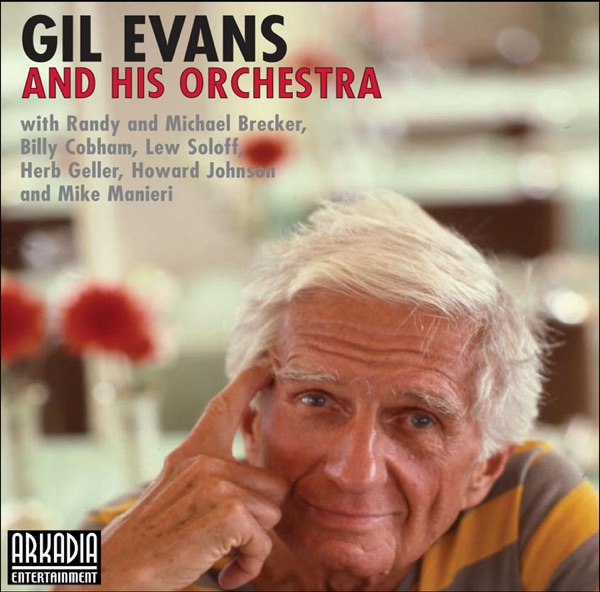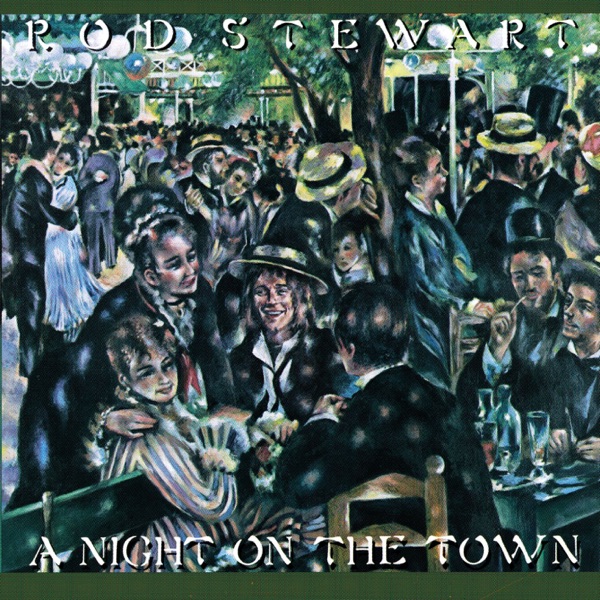サクソフォン・プレイヤー Jimmy Castor 率いる The Jimmy Castor Bunch の代表作。
"It's Just Begun" は多くのサンプリングに使われている模様。僕は詳しくありませんし、なぜそこまで使われるのかは分かりません。
サックス・プレイヤーだけあって、ホーンの使い方とフレーズがカッコいいからなんでしょうかね。
映画 FLAHDANCE のブレークダンスのシーンで使われている(当時全くきづきませんでしたが)のを見ると、意外と Hip & Hop と相性がいいみたいです。
基本的にはファンクです。最初からゴリゴリと押してきます。太めのベースとカッティング・ギターが絡んで、いいところでホーンが入ります。
1972年らしいサウンドですね。