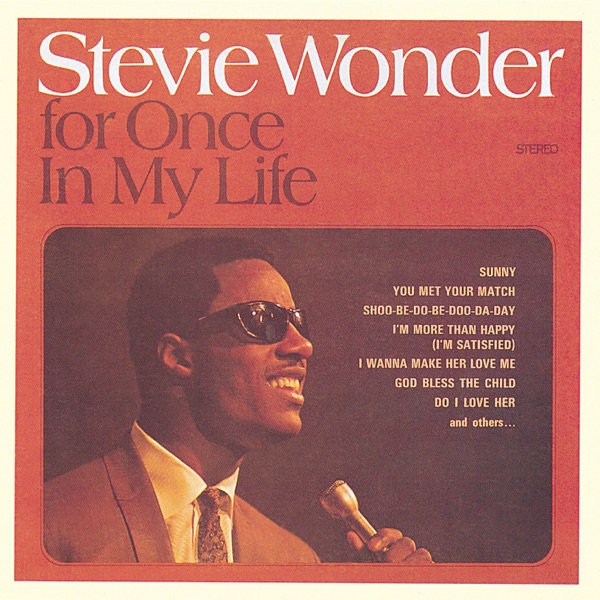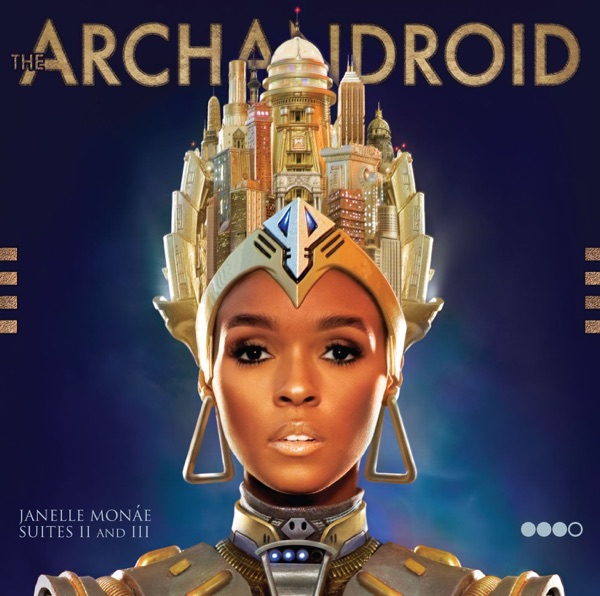マンボキング Machito ですが、それを期待したら期待外れです。
マンボ、ラテンというよりは、ジャズ。アフロ・キューバン・ジャズというのでしょうか。たしかにジャケットに "afro-cuban jazz" と書いてあります。
コンガ、ボンゴ、パーカッションが、ラテン・フレイバーを醸しており、フレイバーを楽しみたい人にはいいでしょう。
Dr. Buzzard's Original Savannah Band 的ですが、一歩間違えばムード音楽。
アフリカのお面のジャケットも、ちょっと違うんじゃないの?、って感じです。