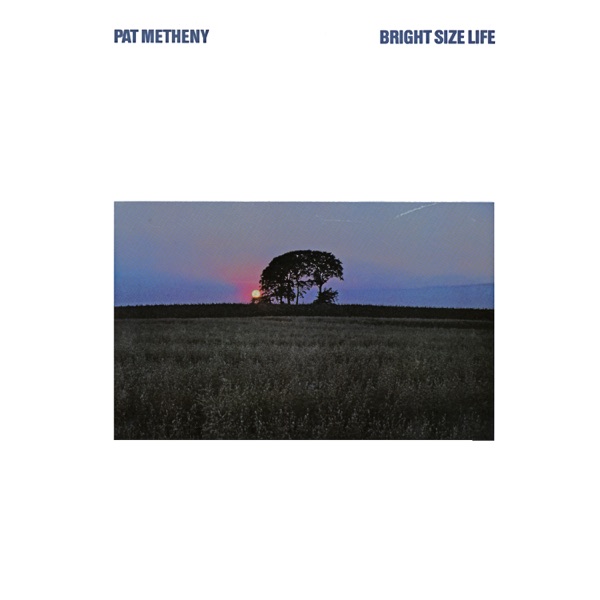基本的には前作の延長ですが、少しエレクトリックの要素が強くなってるかな。
相変わらず、ディスコ、ラップ、ポップの見事な融合に仕上がっています。
特徴づけているのは、やはりそのサウンドでしょうか。
ステディに刻むマイルドなディスコビートに中低音のシンセサイザーが絡む、懐かしさを感じさせるサウンドです。そこにいきなりラップが入るのでビックリしますが。
今回もラップ、ヴォーカルで、鎮座DOPENESS、yoshiro (underslowjams)、田我流、Kick A Showなどが参加する他、土岐麻子が1曲メインヴォーカルで入っています。(土岐麻子の"PINK"もこのアルバムと同時期に発売され、G.RINAの曲も2曲入っています)
今年のグラミーを見ても、USAではブラック・ミュージックが全盛ですが、日本ではロック、ポップス系がメインストリームです。G. RINA のような人がもっと頑張ってほしいですね。